
本漆による「金継ぎ」ワークショップ
欠けてしまった、割れてしまった器をご持参ください。 本漆を使用した伝統的な「金継ぎ」の最初の作業をご体験後、 うるしの駒やがお預かりして、2~3か月程度かけて最後まで仕上げます。
【ご納期延長のお願い】
お陰様で沢山の金継ぎのご依頼を頂いており、通常2~3ヶ月のご納期が、現在3~5ヶ月程度と長くなっております。
丁寧な仕事を心掛けますので、誠に申し訳ございませんが、ご理解とご容赦を賜りますよう宜しくお願い致します。

〇おひとり様体験代3,300円+修理代(目安:3,850円〜)全て税込
*修理代はお持ちいただきました器の破損状態によって異なります。
*ご発送の場合、送料が追加となります。
*会場によって、体験代が変更になる場合がございます。
〇所要時間:1~1.5時間(お持ちいただいた器によって所要時間が異なります)
〇場所:ふくい食の國291 B1F 工芸スペース。その他、条件が整えば出張ワークショップを行います。
※ご注意
ワークショップに参加される方は、汚れてもいいお洋服やエプロンをご持参ください。
ゴム手袋をご用意しますが、「漆かぶれ」が心配な方はご遠慮ください。
「うるしの駒や」金継ぎワークショップ@ふくい食の國291(銀座)のお申し込みはこちらから↓。

「うるしの駒や」金継ぎワークショップとは?

うるしの駒やの「金継ぎ」は、本漆を使用した伝統的な「金継ぎ」のため、4~5工程を2~3ヶ月かけて行います。ワークショップでは、最初の本漆による接着、及び形状復元作業をご体験後、 うるしの駒やがお預かりして、最後まで仕上げます。以下に、ワークショップの内容をご紹介します。
金継ぎワークショップの内容
①金継ぎのご紹介
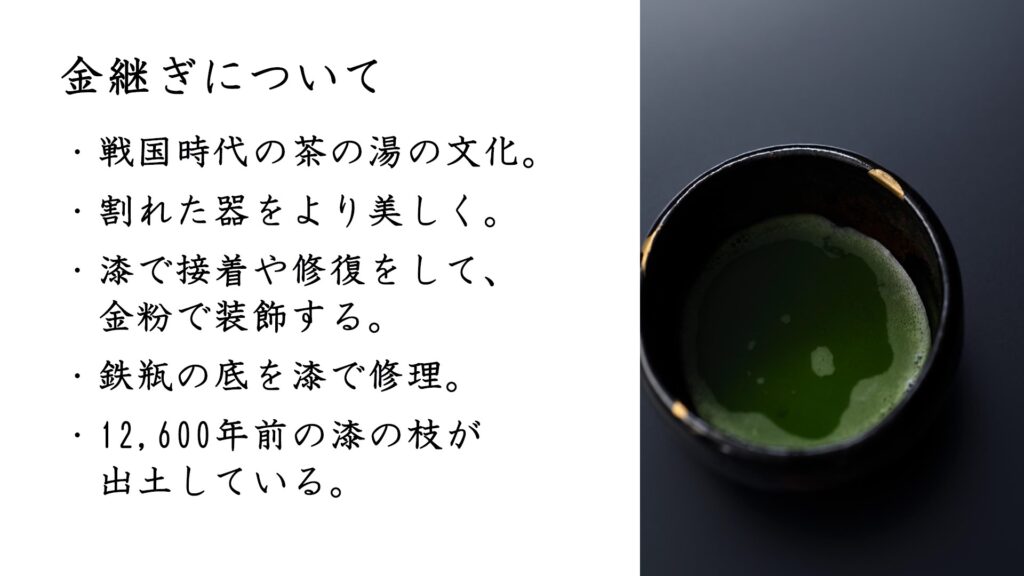
作業の前に、金継ぎについて簡単にご紹介いたします。
②マスキングテープによる下準備

漆で修理する作業の下準備のために、マスキングテープで補修部分を囲むように貼り付けます。

割れた器の場合は、破片をマスキングテープで仮止めします。

③講師による「錆漆(さびうるし)」作りの実演

砥の粉をガラス板に取り出し、水を加えて練ります。

水で練った砥の粉に、地の粉(珪藻土)と、生漆を加えます。

しっかり練り上げた後に、講師から参加者の皆さんに「錆漆」をお配りします。
④錆漆による形状復元や接合

ヘラを使って、器の欠けた部分を錆漆で埋めていきます。
*漆かぶれ対策のため、ゴム手袋をご着用頂きます。

割れた器の場合は、割れた断面に錆漆を塗っていきます。

錆漆を塗った断面を接着し、マスキングテープでしっかりと止めます。
⑤「うるしの駒や」がお預かりし、最後まで仕上げます。
その後はうるしの駒やがお預かりし、以下のような作業を2~3ヶ月掛けて最後まで仕上げます。
錆漆の硬化⇒錆漆研ぎ⇒錆漆(再)⇒錆漆研ぎ(再)⇒高上げ漆塗布⇒高上げ漆硬化⇒高上げ漆研ぎ⇒粉入れ漆塗布⇒金粉撒き⇒粉入れ漆硬化⇒金粉磨き上げ⇒完成
「うるしの駒や」金継ぎワークショップ@ふくい食の國291(銀座)のお申し込みはこちらから↓。

金継ぎワークショップ参加者の声

とっても満足です!
欠けのある商品を持参しましたが、
今回持ち込んだ商品とは違う割れ方の器あったら、また参加したいです。
伝統的な金継ぎの技法や、金継ぎとは何なのかなど、とても丁寧にお教えいただきました。
また、実際の作業では細かなコツや、やり方をお教えいただき、短時間のワークショップでもとても為になりました。
そしてうまくできないところはしっかりフォローしていただき助かりました笑
自分で金継ぎセットを購入してチャレンジすることもできそうです。
今回は欠けを修復する金継ぎでしたが、割れているものをくっつけるのはまた違った手法でしたので、
もしお気に入りのお皿が割れてしまったら、次回も参加したいと思います。
体験せずに、器を直して頂くことも可能ですが、
お気に入りで大事にしている器だからこそ、少しでも自分の手で携わることができ、とても良い経験をさせていただきました。
仕上がりが楽しみだし、仕上がった金継ぎを見ると、
きっと今日のこの体験のことも思い出すと思うので、器への愛着が増しますね!
講師紹介
薮下喜行(やぶしたよしゆき) うるしの駒や代表。金継ぎ師。

うるし業 。1973年福井県鯖江市生まれ。信州大学人文学部卒業後、1996年に黒龍酒造株式会社に入社。 酒造りに従事した後、企画部の創設、「九頭龍」「無二」ブランドの立ち上げなどを担当する。 経営企画部長、企画営業部長を経て退社。 越前漆器の蒔絵の伝統工芸士である駒本長信氏に出会い、天然素材である漆の力に魅了され師事、 2022年に金継ぎを主な業務とする「うるしの駒や」を創業する。 金継ぎ作業の傍ら、漆塗りの薄口容器「うすくちうるし」の製造販売も手掛ける。2024年4月より上野池之端にて「継未金継ぎ塾」を開校。 2021年より福井県立大学大学院経済・経営学研究科博士課程に在学中。 経営学修士。酒造技能士2級。